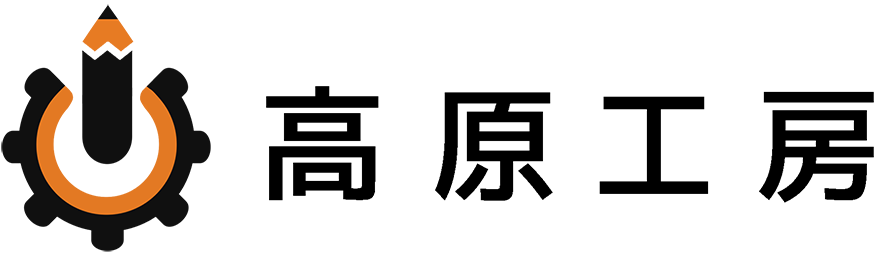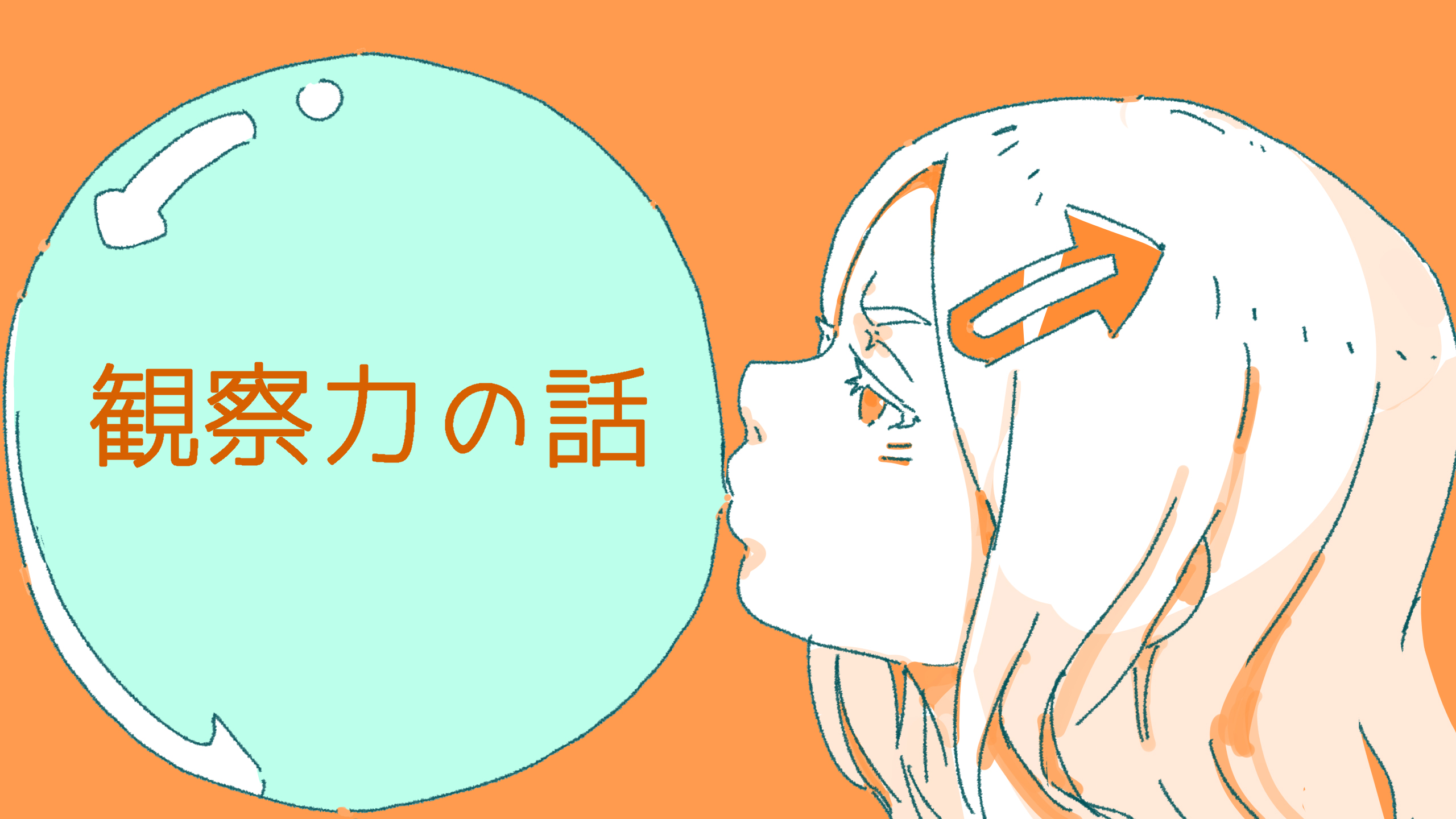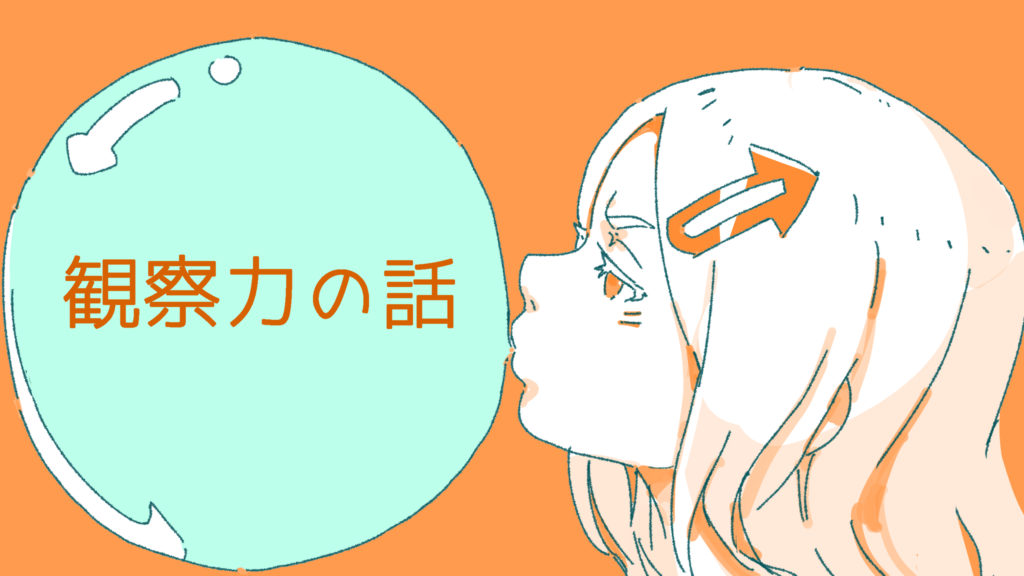モノを見るのは難しい

高原さと(@ART_takahara)です!
今日はですね、絵を描くのに重要な、「観察力」についてお話ししたいなと思います。
ここでいう観察力っていうのは、いわゆる洞察と比較した時の観察っていう意味じゃなくて、いろんなものに気づくっていう意味の観察だけじゃなくて、ただ単純に物を見る力っていうようなこととか、発見する力っていうような部分についてのことです。
で、なぜ観察力を鍛えた方がいいかっていうと、観察力があると様々なことに気づくことができたりとか、違いに気づくことができる、発見することができたりとか、それだけそのインプットする機会が増えるんですね。
インプットっていうのは、前に話したように、何か記憶するっていうだけじゃなくて、自分の中の発想とかアイディア、自分の中から出てくるようなものもインプットに含まれるんですけど
自分の中から湧いてくるインプットも、観察力があると普段生活している中で様々な場面でいろんなアイディアが浮かんでくるということがあるので、観察力を鍛えておくと色々役に立つことがかなり多いかなと思います。
物を作る人だけじゃなくてね。
ただ、この観察するって本当に難しくて。
僕も今回戒めのためにね、いつも通りなんですけど。
自分も観察力がないなっと思うことがよくあります。
本当に何も見えてないなっていうふうに思うんですよね。
ぞっとするぐらい物を見えていないんですよ、人間って。
本当に物が見えてない。
なぜ見えていないかっていうと、その理由は、人は同じことをまず繰り返しますよね。
同じことを繰り返してしまう、繰り返しているっていうのはその物を見ている時も同じで、繰り返し同じ部分だけを見ているんですね。
っていうより、物を見ていなくて、前も話したように物の印象を見ているんですよね。
初めていったときに、ちょっとだけ映像を見るんですよ、一部分の。
例えば人間の顔だったら、目尻の印象とか目と眉のバランスとか、顔のなんとなくの輪郭と、なんとなくの色のバランスとかを見て、その印象を頭に記憶するんですね。
次にその人に会った時は、その印象を照らし合わせて同じ人かどうか判断するというような感じで。
二回目以降会ったりとか、二回目以降同じ場所に行った時っていうのは、ずっとその印象を頭の中で思い出しているだけで、実際の目の前のものは何一つ、何一つじゃないですかね、ほんのちょっとしか見ていないんですね。
なのでそうすると、毎回毎回同じ部分だけしかものを見ていないことになるので、そうすると新しい発見もないですし、当然つまらないものになりがちですよね。
ものを見るっていう行為とか、体験であったりとかが。
そうですよね。
だって、同じ部分しか頭に入ってこないんですから、もうあきたっていうような感じになりますよね。
そうすると、どんどん新しいこと、新しい全然違う場所に行ったりとか、全然違うものを見たりとかしていかないといけないんで。
でもそれって結構限りがあるじゃないですか。
限りがあるし大変なんで。
でも本当は一つのものでも、ものの見方を変えたりとか、注意深く観察すれば、本当にいろんな情報を得ることができるはずなんですね。
なんですけど、同じ印象ばかりを追ってしまうんで、なかなか新しい体験とか新しいインプットに繋がらないと。
そうするとやっぱり人生が速く過ぎてしまうんじゃないかと思います。
ものの味とかの感覚とかもそうだと思うんですね。
味とかにおいとかもそうで。
たぶん本当に感じたものじゃないと思うんですよ。
食べたものとかを何回も食べてたりすると、本当に味わってなくて、味を感じるより先に脳がその味の印象を先に出しているような感じがするんですよね。
だから味がしないっていうか。
おんなじような味になってしまうんですけど。
本当はたぶん注意深く味わうと、毎回毎回新しい発見を得ることができると思うんですよ。
味とかにおいとかいろんな体の五感すべてにおいて。
なんですけど、そういうことをやらずに繰り返し繰り返しおんなじような感じで同じ印象だけを引っ張り出してものを見たりしてしまうと、なかなか新しいインプットとか新しい発見ができないから、これは人生を速く過ぎてしまうということになるんじゃないかなと思います。
19歳までで体感の人生は半分だって誰かがどっかで言ってたんですけど、それもそういう理由だと思うんですよね。
要するに、最初の方はほとんどが新しいものだから、新しい発見として見れるから長く感じるんだと思うんですけど、なかなか人間生きてて大体の行為は一通り、基本的な行為は大体やるじゃないですか、もう二十歳とか、三十歳ぐらいまでに大体みんなやるんじゃないんですかね、一通りのことは。
旅行も行くし、食べ物だっておいしい物とかまずい物とか色々食べるじゃないですか、痛い思いとかも多少はして、っていうことになるんで。
なかなかその繰り返しのパターンの中から抜け出せないというようなことになると、残りの人生はあっという間に過ぎ去ってしまうと。
今まで感じた印象を繰り返してしまうだけというようなことになってしまうので、そうならないために、今回は一応観察だけに限ってなんですけど、今までありふれたものというか同じような印象、同じようなものの見方をしていたものをちょっと、ものの見方とか考え方とか接し方を変えることでいろんな新しい発見とかもできるし、人生が楽しく過ごせるかなと思うので、みなさん観察力を鍛えたらいいんじゃないかなっと思います。
何かに一部分に注目してみる
つづいてこっからはね、具体的な方法についてお話ししていきたいなと思うんですけど。
具体的な方法ってつっても、僕もできていないことも多いんですが、すでに知っているものの中からお話しするんですけど。
まずですね、何かに注目してものを見るようにするっていうのがひとつありますよね。
ぼんやりものを見てしまうと結局そのぼんやり見ている中の印象を追いかけてしまうんで、結局普段って、例えば毎日歩いている道とかってぼんやりもの見てるじゃないですか。
だから何も見てないわけですよ。
そうやってぼんやりものを見ていると、なかなかものの違いとかに気づけなかったりとか、発見するとか、インプットするって難しいと思うんで、そういう時は何か今日はここのポイントに絞って見てみるっというような感じの見方をするといいと思いますね。
これは本当に何でもよくて。
例えば、今日は自動販売機を見てみようとか、あとは今日は色を見てみようとか。
パッとこう歩いていて、道の真ん中に立っていたとしたら、例えば地面だけを見てみるとか、電柱だけを見てみるとか、看板の文字を見てみるとか、そういうパーツ単位のものに注目するだけでもかなり違う発見ができると思います。
なぜなら、こうぼんやりして見てしまうとふわふわっと全体だけを見てしまうんで、やっぱり違いに気づけないじゃないですか。
でも、一ポイントだけを見てるとやっぱりそのものが見ている部分が絞られるんで、あれこれってこんなんだっけっていうふうに思えると思うんですよね。
例えば看板とかひとつとっても、電柱とかに貼ってある張り紙とかひとつとっても。
改めて注目してみると、知らなかった情報とかがのっているはずなんですよね。
そういうパーツ単位だけじゃなくて、もうちょっとその絵的な話でいくと、例えばそのもののシルエットとかに注目してみたりとか、色の境界に注目してみたりとか、キャストシャドウを探してみる、キャストシャドウ、落ちている影を探してみたりとか本当に何でもいいと思うんですけど。
パッと何かものを見た時に、ここっていうところに注目して、毎回そこを変えたりとかしてみる。
で、一回注目してみたら次に注目してみた時に違いに気づけたりするじゃないですか。
すると思うんすよ。
人と会った時も、何気なくその人の服装とか顔とかをぼんやり見てたら、なかなか違いって気づけなかったりとかすると思うんですけど、例えばその人の眉毛だけに注目してみるとか、眉にいっちゃう人だったらね。
そうすると、今度他の人と会った時に、その人の眉毛の形状と比較できるじゃないですか。
比較すると思うんですよ、無意識にね。
そうすると、あっこの人の眉は目と結構離れているけど結構厚みがある眉毛だなっとか、結構それがやわらかい印象につながっているなっとか、もしくは眉毛と目の距離が近いからこの人はちょっと男らしい印象の人に見えるんだなっとか、そういうことにこう比較して気づけると思うんですよ。
注目しておけば、他の何かを見た時にそのポイントに、同じポイントに注目すればそれで比較することができるじゃないですか。
っていう感じで、何かポイントに注目するっていうのはすごく簡単なんで、結構やってみるといいかもしんないですね。
その意識さえあればできると思います。
僕もやろうと思わないとできないんで、やろうと思うんですけど。
注目するのはたぶん一点でいいと思いますね。
二点以上見るっていうのはすごく難しいと思うんで。
その一点のポイントを日にちによって変えたりとか、場所によって変えたりとかしていくことがいいかなっと思うんですよね。
で、それを記録できたらすごくいいと思うんですけど
僕は記録するのが下手なんで
ただそこで、絵が描ける人は絵に描いておけばいいんですよ。ここでね。
その場で描けたらもちろんいいんですけど、その場で描けなくても何か気が付いたらそれをちょっとメモ書きしておいて、後でそれをちょっと思い出しながら描いたりとか。
毎日会っている人とか、毎日見てるものとかだったら、そこまで、すぐ確認できるじゃないですか。
だから別にその場で描いても描けなくても、後から描くことっていうのも難しくないと思うんで。
そういう感じで記録できるっていうのも、絵のいいところだなと思うんで。
何かポイントに注目して違いに気が付いた時にそれを絵で描いておくというようなことをしてみるといいかなと思いました。
やっぱりぼんやり見てしまうとね、どうしてもなんも頭に入ってこないと思うんで。
何かに注目する時のどこに注目すればいいかっていうのは最初わからないかもしれないんで。
僕もいろいろ試したりしているんですが。
質感に注目するとか、色に注目する、シルエットに注目する、ものの接合部に注目したりとか、絵描きで多いのは服のしわを見ている人が結構いますね。
あとは、僕も結構見るのは、ハイライト、スぺキュラ、ものが共鳴反射してキラッと光っているような部分の形状をみると。
その部分的にね、自分が好きな部分とか、本当に何でもいいと思うんすよ、赤い部分に注目しようとか、ピンクの部分が好きだからピンクを見ようとか。
そんな感じでもいいと思うんで。
そんな感じでね、毎回毎回ちょっとずつ注目ポイントを変えていくということをやると、かなりいろんなことに気づけたりとかするし、毎日がね、それだけで結構まあまあ大変っていうか、まあまあ忙しくなると思うんで。
毎日毎日同じことの繰り返しでつまらないなというふうに思っている人は、そんな感じでね、何かに注目してみると結構生活が多少豊かになるかなと思います。
それを絵で描いておいてね、本にできたりしたらものすごくいいですよね。
そんな感じで、試してみてください。
対象への接し方を物理的に変えよう
はい。これで終わろうかなって思ったんですけどもう一個だけ紹介しておきますね。
っていうのも、さっきの話結構精神論的な話になっちゃったなと思ったんで。
もうちょっと具体的にやれることを考えようかなと思ったんで。
精神論ではない、具体的な案ももちろん出したんですけど、注目しようとかって結局その意識の問題じゃないですか。
意識の問題だとなかなかこうやっぱり、脳みそって結局自動で動いちゃうんで。
なかなか今まで抱いた印象とかを塗り替えるとか、これで新しい発見をするっていうのもなかなか難しいのかなっていうふうに思ったりするんで。
もちろん何かに注目するっていうのもやってほしいんですけど。
それよりもね、物理的に対象に対する接し方を変えてしまうというのがひとつあるかなと思います。
脳っていうのは結局単体で存在しているものじゃなくて、単体で機能するものじゃなくて、行動した時にそれに付随して動く、自動的に動くものであって、大したものでもないかなと最近思うようになったんですけど。
要するにね、行動してしまえばそれに付随して結局新しいインプットっていうのが出てくるんですよ。
だから新しい行動をすればいいだと思うんです。
ものに対する接し方の行為そのものを変えてしまうっていうのがいいいかなと思うんですね。
例えば、簡単な例だとしたら、自分の部屋にいるじゃないですか。
部屋にいて普段大体動くポイントって決まっていると思うんですよね。
だけど、寝っ転がってみたりとか、そこまで極端じゃなくてもいいかな。
なんかほんとに物との距離感とか接し方を変えたらいいと思うんですよね。
例えば、壁とかに触ってみるとか、触ってなかった所に触ってみる。
とかすると、触るっていうことをするには、物に結構距離を近づけないといけないじゃないですか。
そうすると、また触ったことでその質感の印象とかが体に入ってくるんで、そうすると、今まで触ったことがなかったものに触ったっていうことは、必ずそこで新しいインプットになると思うんですよね。
首をかしげてものを見てみたりとか、あとはそうですね、例えばさっきの道の話で言ったら、普段歩いている道で何か観察したいとすると、歩くスピードを変えてみたりするのがいいですね。
これもその物理的に何かものを変えているじゃないですか。
この注目しようとかそういうような話じゃなくてね。
で、ゆっくり歩いてみると、例えば、絶対ゆっくり歩くっていうのが結構特殊な状態なので、
そうすると必ず何かに気がつくと思うんですよね。
その情報の入り方が、スピードも変わってくるじゃないですか。
結構早歩きで今まで歩いていたとしたら、景色が流れていくスピードが、今までの印象だとある一定のスピードでいつも通り流れていったと思うんですけど、情報の処理のスピードが。
それがゆっくりになると、急に情報の入り方が変わってくるわけなんですよ。
目の中に入ってくるね。
そうすると、例えばもののシルエットがもうちょっと見えてきたりとか、空間の印象が変わったりとかするかもしんないんで。
その感じのこともありですよね。
結局その目って、目を変えるってなかなか難しいじゃないですか。
例えば、目を細めるとかそういうのももちろん物理的にあるんですけど、でも目を普通に開いて見てるだけだと、なかなかそれで違うものに注目するっていうのも難しいちゃ難しいんで。
そうじゃなくて、実際に目と対象物の距離を変えたりとか、目がある位置を変えたりとか、目が動くスピードを変えたりとか、っていうような感じで、もしくは触りながら見てみるとか、そんな感じでこう何か、こう具体的な行為とかを付け加えてものを見ると、自然とそれに脳が付随して、脳が反応してたぶん今までと違う動きをするはずなんですよね。
そういうような感じで、ものの見方を変えるんじゃなくて、ものとの接し方を具体的に変えるっていうふうのは結構インプットには重要かなっと思います。
それこそなんか、観察するんじゃなくて壊してみるとかね。
知り合いのエフェクトをつっくているCGのアーティストとかも、何か燃やしたりとかね、物を燃やしたりとか。
木の実みたいなものを割ってたりとかね、割ってみて破片の動きを見てみたりとか。
そういう、自分の目っていうか意識とか、そういう曖昧なものじゃなくて、実際具体的に目の前でこう何か起こしてしまうっていうようなことをしてみるといいんじゃないかなっと思いました。
そうですね、振り返ってみるとかだけでも結構違うと思いますね。
振り返るってなかなかポイントポイントとかでしかやらないじゃないですか。
いつも振り返ってみたことない所で振り返ってみるとか、あとは横を見てみるとかね、横を見てみるとかだけでもものの見え方って変わってくるんで。
それだけでもかなり違う感じはしますね。
そんな感じでいかがでしょうか。
あっ僕が最近やった例だと、やっぱり触ってみるっていうのはいいかなと思います。
僕、結構お茶が好きなんで、ティーバッグのやつなんですけど、よくそれを飲むんですけど、そのティーバッグの形状を観察してみたら、どうもこの輪っかになっているっていうことに気がつきましてですね、これは触らないと絶対気づかないですよね。
そんな、当たり前っちゃ当たり前なのかもしれないですけど、真ん中を輪っかにすることでお湯に触れる面積が増えるからかなと思ったりとか、ティーバッグの紙のくっつけるところのくっつけ方とかをみて、別に接着剤が必要のないつけ方をしてるんじゃないかなとか
熱を当ててつけているのかなとかいうようなことを、触ってみてね、触って動かしてみたらわかったり、わかったりっていうか、そういうふうなインプットに繋がったんで、そこでちょっとまた調べてみようかなっというふうな興味にも繋がったりしたんで。
そんな感じで物の接し方を変えて見るようにしたいなと僕は思っています。
これからね、もっといろんなものの見方とか感じ方とかを試していきたいなと思うんでね。
最近ちょっと感覚が鈍くなってきているような気がしているんで、その辺を解消していくためにもおんなじようなものに対する接し方とか見方とかをしないで、前回のチャプターでいったような、何かに注目したりとかあるいは触ったりとか、角度を変えたりとかしてね、接し方を変えたりとかして、インプットの量を増やしていって新鮮で楽しい人生を送れたらいいなと思いました。
みなさんぜひ参考にしてみてください。